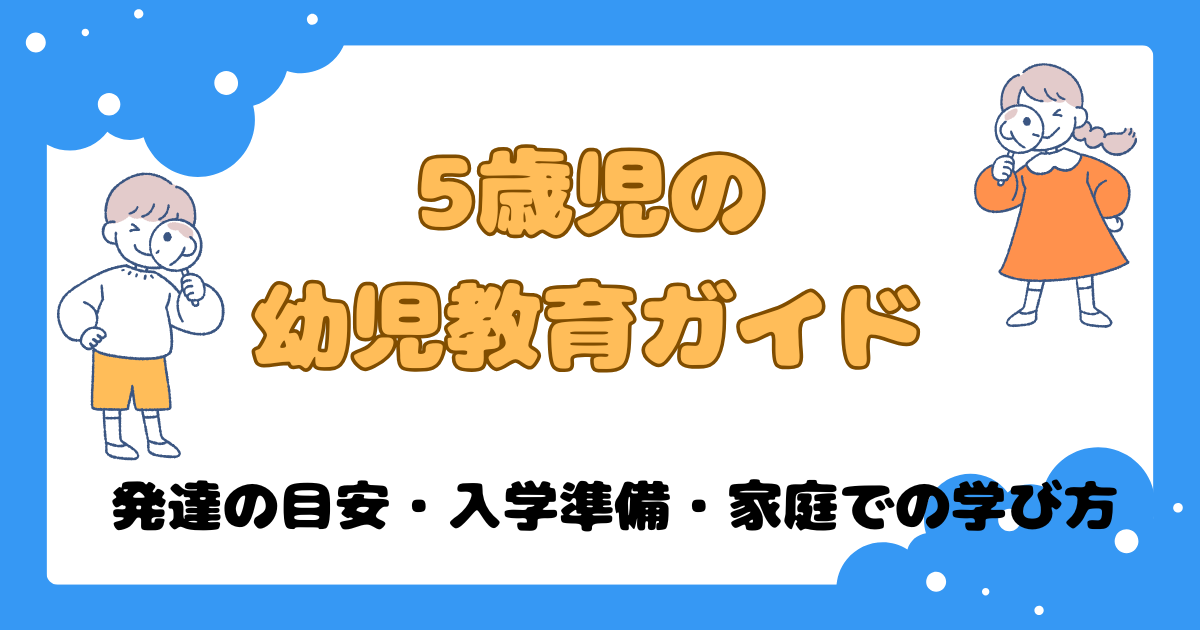
5歳になると、「なんでも自分でやりたい!」という気持ちが一層強くなり、友だちとの関わりもぐっと深まってきます。
同時に、小学校入学も少しずつ意識される時期。
親としては
「発達は順調かな?」
「入学までにどんなことを準備したらいいんだろう」
と心配になることもありますよね。
でも、安心してください。
大切なのは特別な準備ではなく、日々の生活の中で自然に学びや成長を支えることです。
この記事でわかること
・5歳児の発達の目安
・小学校入学に向けて育てたい力
・家庭での具体的なサポート方法
・共働き家庭でも続けられる工夫
これらを具体例とともにわかりやすくまとめました。
親だからこそできる関わり方を、この記事で一緒に見つけていきましょう。
5歳児はどんな時期?発達の特徴と成長のポイント

5歳は、幼児期の学びを「自分の力」に変えていく時期です。
体のコントロールが安定し、言葉や思考も一段深まります。
友達関係が広がるにつれて、感情のやり取りやルール意識も育ちます。
こうした特徴を押さえておくと、家庭の関わり方がぐっと具体的になります。
心と体のバランスが整い始める
✅全身運動が滑らかになり、体幹が安定して長く活動できるようになります。
✅手先の巧緻性も高まり、ボタン掛けや紐結び、はさみ・のりの扱いが上達。
✅情緒面では、気持ちの高ぶりからの切り替えが少しずつ上手になります。
家庭では、朝の身支度を「順番どおりにやる遊び」にしたり、縄跳び・ケンケン・ゆっくり平均台(床に貼ったテープでもOK)でバランス感覚を磨きましょう。
雨の日は、風船リレーや新聞紙ボール投げで「軽い負荷×達成感」を積み重ねるのがおすすめです。
論理的思考・言語表現がぐんと伸びる
✅出来事の「理由」や「手順」を筋道立てて話せるようになり、因果関係への興味が増します。
✅絵本や体験を、原因→結果→感想の流れで言葉にする練習が効果的。
✅家庭では、料理や工作を「①準備→②作業→③片づけ」と区切って進め、各段階で「次は何をする?」と子どもに予測させます。
読み聞かせ後は「誰が・いつ・どこで・なにを・どうした」を5W1Hカードで確認したり、好きな場面を1枚絵にして「説明プレゼン」してもらうと、語彙と論理が同時に伸びます。
-
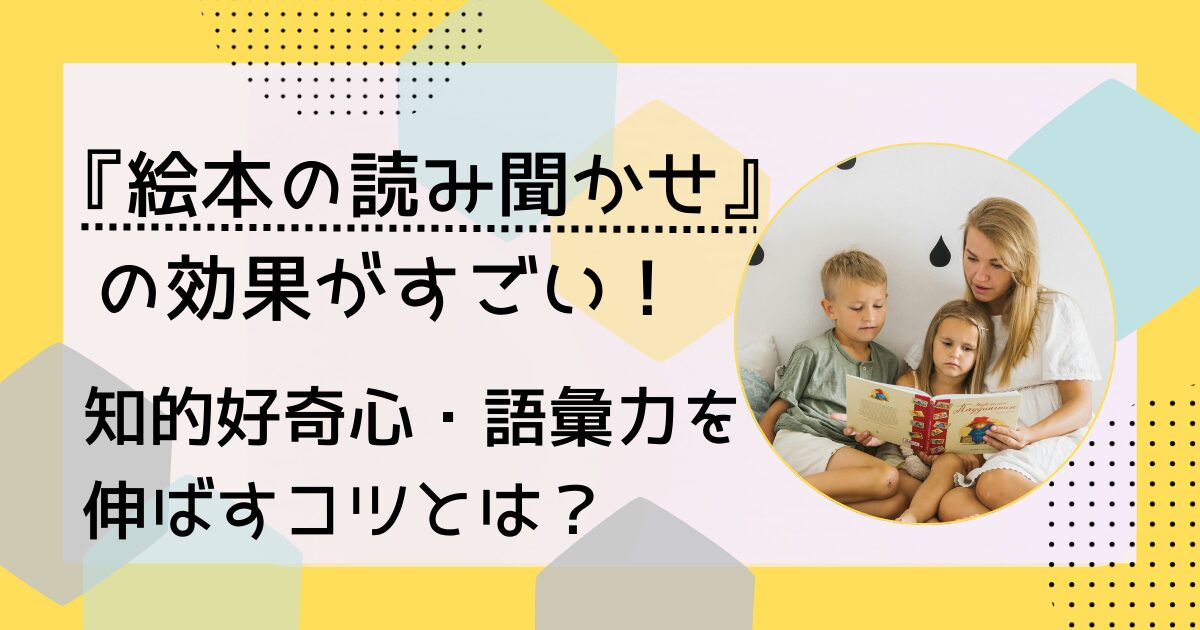
-
『絵本の読み聞かせ』の効果がすごい!知的好奇心・語彙力を伸ばすコツとは?
こんにちは、子育てに奮闘中の皆さん。 お子さんと過ごす時間の中で、「もっと成長を促してあげたい」「何 ...
続きを見る
友達関係や社会性がより重要になる
✅友達と役割分担したり、意見をすり合わせたりする機会が増えます。
✅勝ち負けの感情も濃くなり、そこから「切り替え」「相手の立場に立つ」練習が始まります。
✅家庭では、すごろくや協力型ボードゲームで「順番・ルール・役割」を体験。
✅トラブルがあった日は「事実→気持ち→次の作戦」を短く整理して振り返ります
(例:「おもちゃを取られて悲しかった。次は“貸してね”と言ってみよう」)。
共感の言葉(「悔しかったね」)と、行動の選択肢を並べる声かけがカギです。
5歳児の発達の特徴をひと目でチェック
5歳は、心と体が大きく成長する時期です。
家庭での関わり方を考えるヒントとして、この時期に育つ力と、親ができる具体的なサポート方法を以下の表にまとめました。
| 分野 | 発達の特徴 | 家庭での具体的な関わり方 |
| 心と体 | ・体幹が安定し、活動時間が伸びる ・手先が器用になる ・気持ちの切り替えが少しずつ上手に | ・朝の身支度をゲーム化 ・縄跳びや平均台でバランス感覚を磨く |
| 思考・言語 | ・出来事の「理由」や「手順」を話せる ・因果関係への興味が増す | ・5W1Hカードで絵本を振り返る ・料理や工作の手順を予測させる |
| 社会性 | ・友達と役割分担する ・勝ち負けの感情からルールを学ぶ | ・ボードゲームでルールを体験 ・トラブル後に気持ちを整理して振り返り |
親の関わり方|子どもの成長を促すためのヒント

5歳児の発達の特徴を理解したら、次はそれをどのように日々の関わりに活かすかが重要です。
ここでは、子どもの「もっとやりたい!」を引き出し、学びを深めるための具体的なヒントをご紹介します。
「できた!」の過程を認める声かけ
子どもが何かを成し遂げた時、「すごいね!」と結果だけを褒めるのではなく、「最後までやり切ったね」「ここを頑張ったんだね」と、その過程や努力を具体的に言葉にして認めましょう。
そうすることで、失敗を恐れずに挑戦する気持ちが育ち、自己肯定感が高まります。
-
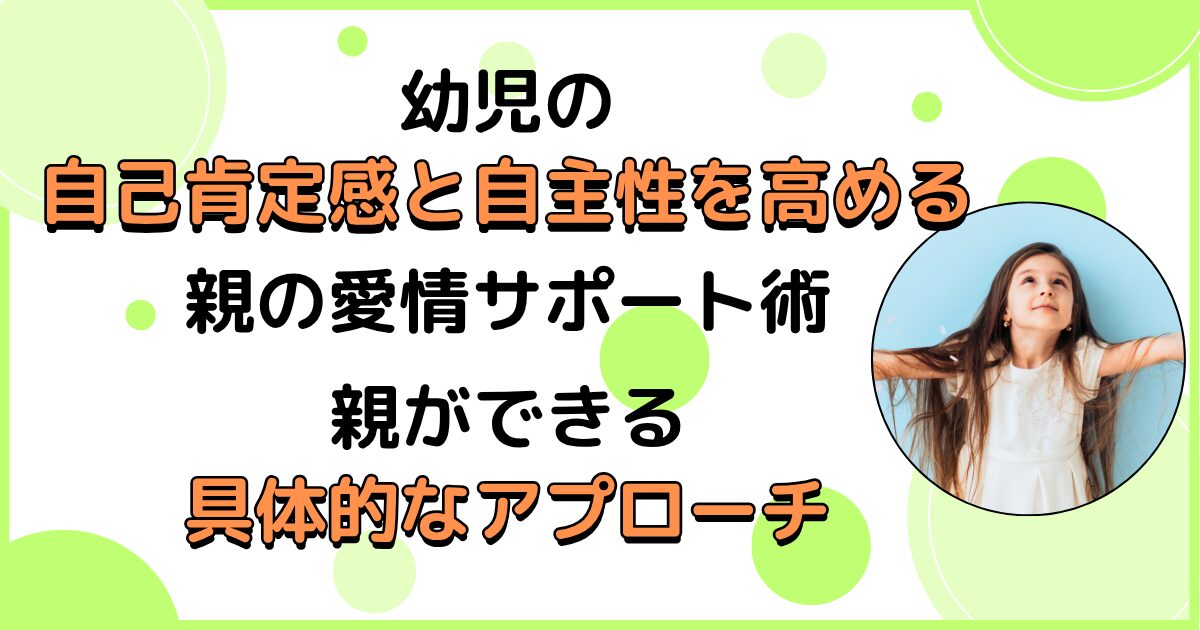
-
幼児の自己肯定感と自主性を高める親の愛情サポート術|親ができる具体的なアプローチ
「うちの子は、なんだか自信がないみたい…」 「もっと自分で考えて行動できるようになってほしいけど、ど ...
続きを見る
子どもの「なぜ?」に寄り添う質問
子どもが興味を持ったことに対し、親が正解を教えるのではなく、「なぜそう思ったの?」「どうしたらいいかな?」と質問を投げかけましょう。
これにより、子どもは自分で論理的に考える力が身につきます。
また、親自身も「私はこう思うんだけど、どう?」と意見を伝えることで、対話がより一層深まります。
-
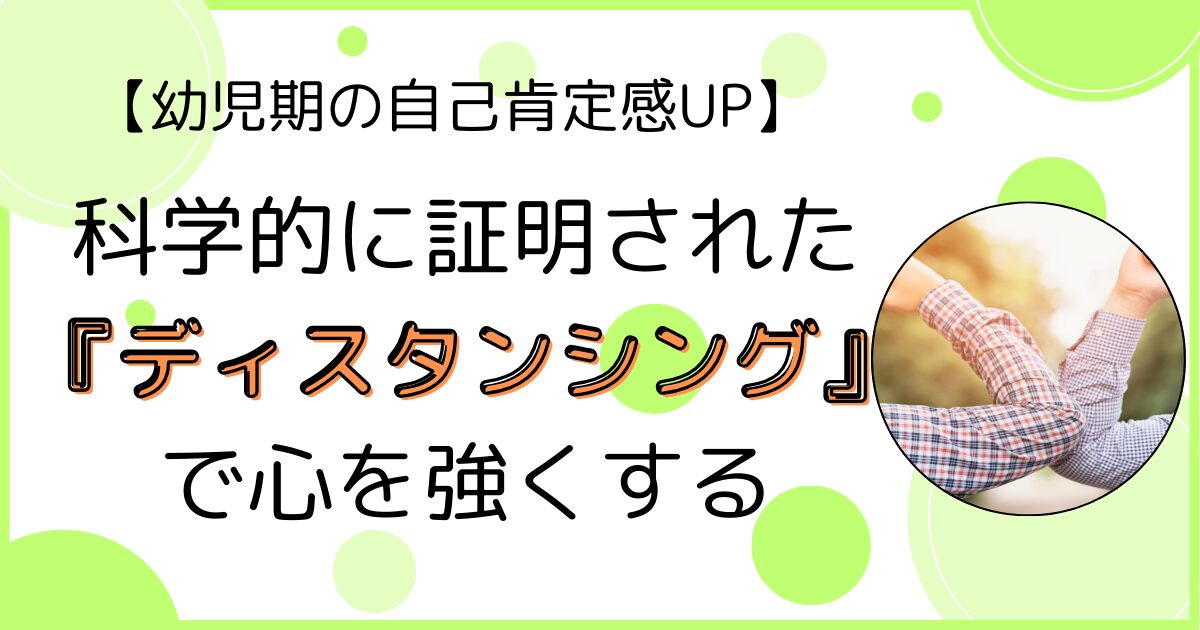
-
【幼児期の自己肯定感UP】科学的に証明された『ディスタンシング』で心を強くする
「うちの子、すぐに『もうダメだ…』って言うんです…」 「失敗すると、すぐに泣き出しちゃうんです…」 ...
続きを見る
遊びや学びを「楽しむ」姿勢を見せる
親子でボードゲームをする時、家事を手伝ってもらう時、親が心から楽しむ姿勢を見せることが大切です。
「一緒にやると楽しいね」「この遊び、大好き!」といったポジティブな言葉は、子どもの意欲を大きく引き出します。
また、作品が完成した際には「どうしてこの色にしたの?」と尋ねることで、子どもの工夫や思いに寄り添い、自己肯定感を高めることにつながります。
5歳児の発達の目安|小学校入学前に育てたい力

入学後に必要なのは「学力そのもの」だけではなく、学びを続けるための土台です。
ここでは、5歳で意識して伸ばしたい5つの力と、家庭での具体的な育て方のポイントをまとめます。
運動能力(跳ぶ・走る・体幹の安定)
✅片足跳び・縄跳び・段差ジャンプなどで下肢の力とバランスを育てます。
✅投げる・受ける・よけるの三拍子が揃うと、集団遊びにも自信がつきます。
✅日常では、登園ルートにミニ障害物コース(白線の上だけ歩く、三段ジャンプなど)を入れたり、夕方に「3分間チャレンジ」で縄跳び回数を記録。小さな積み上げが体力と自己効力感を同時に伸ばします。
認知力・思考力(数・簡単なルール理解)
✅数の対応(数量と数字が対応する感覚)、比較(多い/少ない・長い/短い)、順序やパターン認識が土台になります。
✅買い物で「合計はいくら?」を一緒に考えたり、洗濯物を「色→サイズ→家族別」に仕分ける分類遊びを。
✅カードゲームで「同じ・違う」「大きい順」を扱うと、ルール理解とワーキングメモリの両方が鍛えられます。
言語力(自分の考えを説明できる)
✅語彙の増加だけでなく、理由づけ・具体例・結論の流れで説明する力がポイント。
✅「なぜそう思ったの?」と理由を聞き、親も自分の考えを短くモデル提示。
✅絵日記や「今日のベスト3」発表(嬉しかったこと・びっくりしたこと・頑張ったこと)で、出来事→考え→気持ちを言葉にする習慣を作ります。
社会性・協調性(ルールを守り、友達と遊べる)
✅ルールの理解→自発的な遵守→役割を果たす、の順に育ちます。
✅家族ゲームでは“ルール係”や“時間係”など小さな役割を交代制に。
✅片づけも「誰が何分でどこを担当する?」と作戦会議してから開始すると、協力体験が成功体験に変わります。
自己肯定感と自立心(身の回りのことができる)
✅「できた!」の積み重ねが自信の源。
✅身支度・片づけ・連絡の受け渡しなど、入学後の生活に直結します。
✅チェックリスト(絵アイコンでOK)で“自分で完了”できる環境を用意し、結果だけでなく過程の努力を言葉にして認めます
(例:「最後までやり切ったね」)。
✅失敗時は「次の一歩」を一緒に考え、挑戦が続く設計に。
家庭でできる幼児教育|5歳ならではの学び方

特別な教材や長時間は不要です。
5歳の学びは、生活と遊びの中に自然に組み込むのが最短ルート。
「短く・楽しく・毎日少し」を合言葉に、無理なく続けましょう。
日常生活の中での学習(買い物・料理・時計)
⭐買い物では「合計」「おつり」「どちらが安い?」で数感覚を養い、料理では“手順・計量・時間”が学びの宝庫。
⭐時計は“やることタイマー”(5分砂時計やキッチンタイマー)で体感から入ると定着します。
例)「カレーの材料は何個ずつ要る?」「5分経ったら味見しよう」など、行動と数・時間をつなげる声かけがコツ。
遊びを通じた学び(ボードゲーム・創作遊び)
⭐ルールのある遊びは、順番待ち・記憶・戦略を一度に鍛えます。
⭐創作遊び(ブロック・レゴ・廃材工作)は、設計→試行錯誤→改善の流れを自然に経験できます。
⭐お題カード(「動物の家」「空飛ぶ車」など)を引いて作ると、想像力と発表力が同時に伸びます。
⭐完成後は「工夫した点」を一言でプレゼン。
自然体験や社会体験(遠足・買い物体験)
⭐季節の移ろい、天気、公共マナー、やり取りの言葉 ―― 外には学びが詰まっています。
⭐近所の公園を観察マップ化して、見つけた植物や虫をシールで記録。
⭐商店街では「こんにちは/お願いします/ありがとう」を親子で練習し、簡単なやり取りに挑戦。体験と言葉が結びつくと記憶が強く残ります。
共働き家庭でも取り入れやすい工夫

忙しいからこそ、続けられる仕組みが最優先。
ポイントは「所要時間を10〜15分に設計」「家庭内の役割分担」「家事の省力化」です。
平日の学びは短時間+習慣化
✅夕食前や入浴後に「学びの固定枠」を10分つくります。
👉内容は、読み聞かせ/ワーク1ページ/パズルのいずれかを日替わりで。
✅時間より「毎日続くこと」を評価し、完了シールで可視化。
👉親が忙しい日は、音読を録音してもらい、後で一緒に聞くのも◎。
休日に「体験」を積み重ねる
✅平日にできない「長めの外遊び・図書館・博物館・工場見学」をまとめて。
👉前日夜に「行き先・やりたいこと・持ち物」を子どもと決めると主体性が育ちます。
✅帰宅後は写真を見ながら「3行ふりかえり」(楽しかったこと/発見/次やりたいこと)で記憶が定着。
-
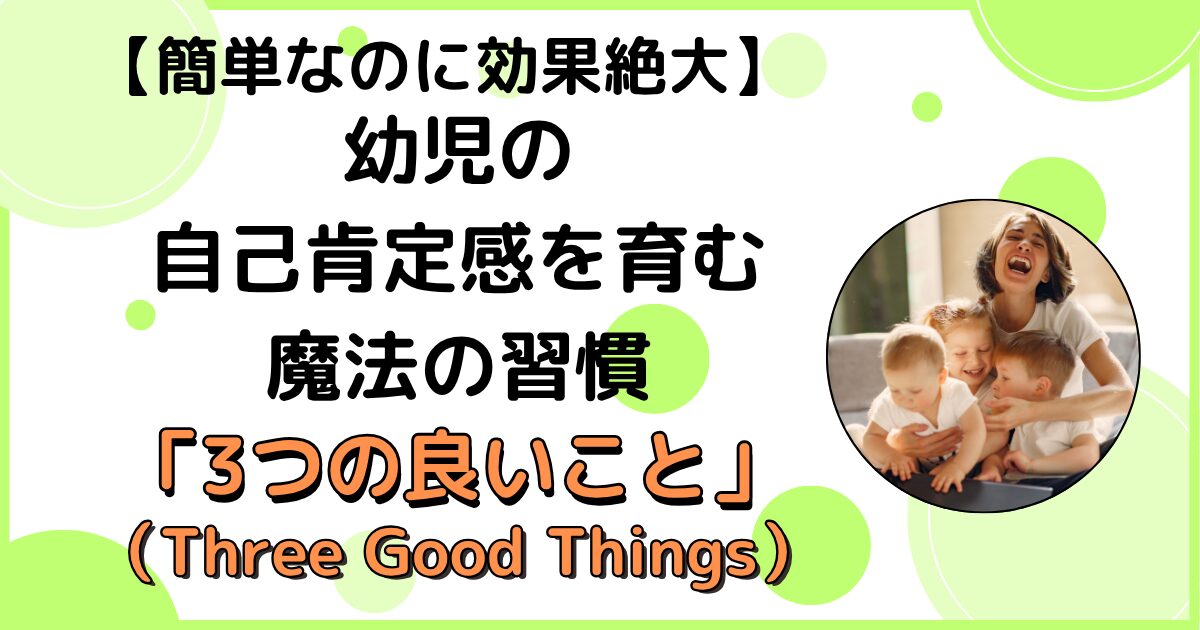
-
【簡単なのに効果絶大】幼児の自己肯定感を育む魔法の習慣「3つの良いこと(Three Good Things)」
「毎日バタバタで余裕がない…でも、わが子のキラキラした笑顔は絶対守りたい!」そう願うママ・パパへ。 ...
続きを見る
時短家事で子どもとの時間をつくる(冷凍食品・宅配サービスなど)
✅ミールキット・冷凍野菜・作り置きを活用し、調理は“混ぜる・ちぎる・並べる”の子ども担当を設定。
✅配膳・片づけも「タイムアタック」でゲーム化します。
👉洗濯は色分け係、清掃はほこりパトロールなど、家事を学びに変えると時短と育ちが両立します。
-
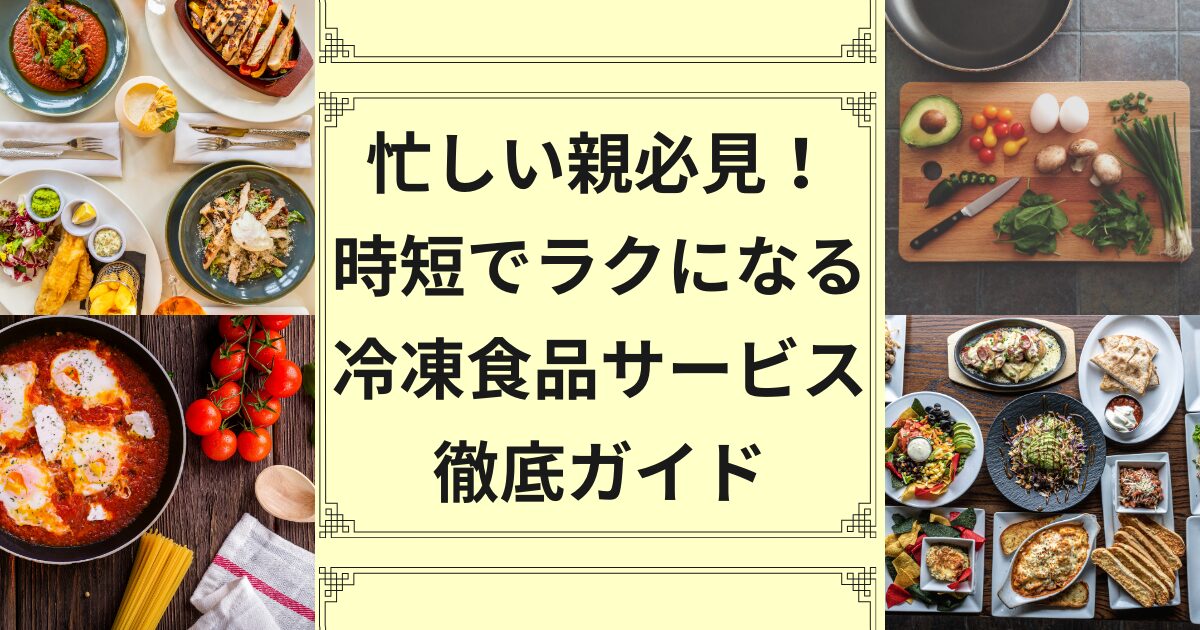
-
忙しい親必見!時短でラクになる冷凍食品サービス徹底ガイド
「仕事、家事、育児……毎日時間が足りない!」と感じる親御さんは多いのではないでしょうか? 特に夕食の ...
続きを見る
共働き家庭の「無理なく続く」ヒント
忙しい毎日でも、子どもとの大切な学びの時間を作ることは可能です。
平日の短時間学習から休日の体験活動まで、無理なく続けられる工夫を以下の行動計画表で確認しましょう。
| 時間帯 | ポイント | 具体的なアクション例 |
| 平日 | 短時間×習慣化 | ・夕食前・入浴後の10分間固定枠 ・読み聞かせ/ワーク/パズルを日替わり ・音読を録音し、後で聞く |
| 休日 | 体験の積み重ね | ・図書館・博物館など、長めの外出 ・前日に子どもと相談して計画 ・帰宅後に「3行ふりかえり」 |
| 毎日 | 家事のゲーム化 | ・調理や片づけを子どもに任せる ・「タイムアタック」や「役割分担」 ・ミールキット・作り置きで時短 |
5歳から始めたい習い事・教材の選び方

「好き」「通いやすい」「無理のない費用・頻度」が三本柱。
家庭学習とのバランスを見ながら、体験レッスンで「相性」を確認しましょう。
-
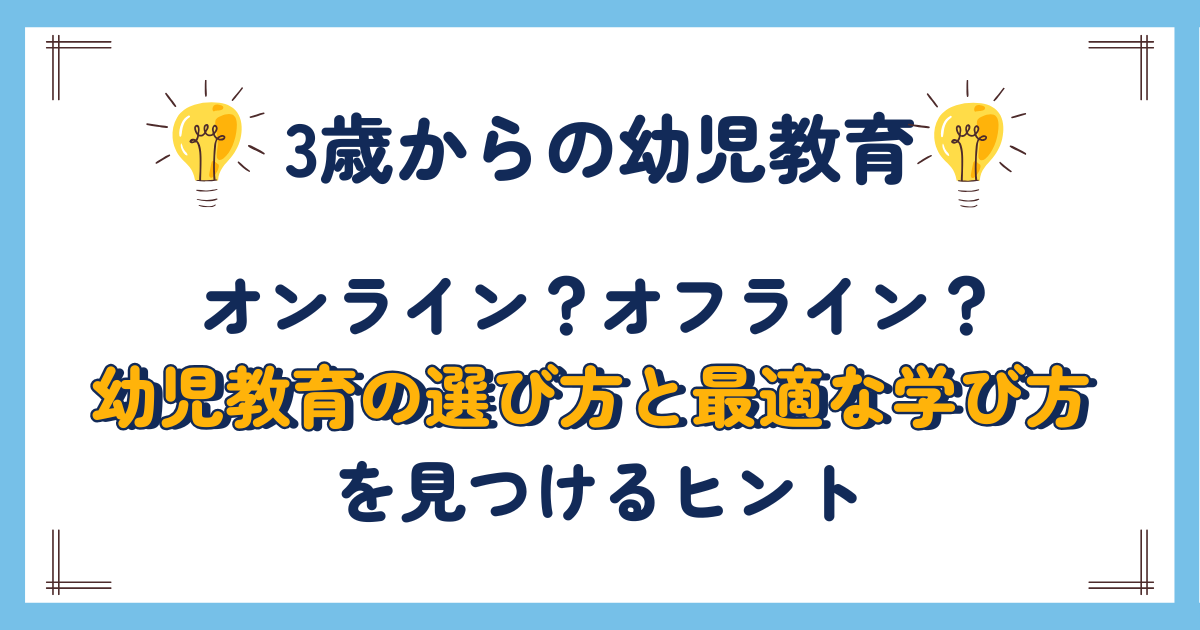
-
3歳からの幼児教育:オンライン?オフライン?幼児教育の選び方と最適な学び方を見つけるヒント
お子さんが3歳を迎える頃、「そろそろ幼児教育を考えないと…」と、多くのパパ・ママが初めて本格的に「教 ...
続きを見る
人気の習い事(英語・ピアノ・スイミング・プログラミング)
✅英語は「歌・絵本・会話ごっこ」中心の教室を。
✅ピアノは「姿勢・リズム・音あそび」から入る教室を。
✅スイミングは体力づくりと達成感に優れています。
✅プログラミングは「順序・試行錯誤」の基礎を楽しく学べます。
判断軸は「子どもが自分から行きたがるか」「先生との相性」「1〜2か月継続後の表情」。
競うより「続けられる心地よさ」を重視します。
通信教育・ワーク教材の活用法
✅1日5〜10分で終わる分量を選び、リビングに「すぐ出せる定位置」を用意。
✅親のサポートは最初の2分で「やり方の確認」だけにし、残りは見守りに回ると自立が進みます。
✅丸つけは「努力コメント」を添えて返却し、月末にファイル化して成果を見える化。
✅「成長アルバム」は最高のモチベーション源です。
絵本・図鑑・辞典で知識を広げる
✅テーマ読み(恐竜の週・宇宙の週など)で興味を深掘り。
✅図鑑→実物観察→関連絵本の順に回すと理解が立体的になります。
✅辞典はことばさがし遊び(「“は”で始まる面白い言葉を3つ見つけよう」)で親しみを。
✅読み聞かせの最後に「今日の新しい言葉」を1つだけ復唱すると、無理なく語彙が増えます。
小学校入学に向けて整えたい生活習慣

『自分で準備して、自分で切り替える』この生活スキルがあるだけで、小1の毎日が格段に楽になります。
今から少しずつ、家庭の仕組みを整えましょう。
早寝早起きと食習慣
就寝・起床は毎日ほぼ同時刻に。
朝は水分→朝日→軽い運動→朝食の流れを固定化。
朝食は主食+たんぱく+野菜を基本に、前夜のスープや作り置きで時短しましょう。
長期休みは学校時間割に近い生活を1〜2週間前からリハーサルすると、新学期の負担が軽くなります。
着替え・片づけ・身の回りの準備
見える収納・ラベル・動線の短さが自立のコツ。
翌日の持ち物はチェックリストで前夜完了。朝は確認だけにします。
服は上下セットで畳む、ランドセル想定でA4トレーを用意するなど、迷わない仕組みを先に作るとスムーズです。
学習環境を整える(机・文房具)
静かに集中できる“自分の場所”を決め、文具は必要最小限を取りやすく配置。
リビング学習なら、家族の動線とテレビ音を避け、照明と椅子の高さを子に合わせます。
始業前に今日やることメモを親子で3行だけ書き、終わったらチェック。
やる→終える→片づけるの一連が身につきます。
よくある質問(FAQ)

5歳児の子育ては、期待とともに多くの不安が生まれる時期です。
ここでは、保護者の方々からよくいただくご質問にお答えします。
お子さんの発達や学習、生活習慣に関する疑問を解消し、安心して子育てに取り組むためのヒントにしてください。
Q1. うちの子、ひらがなや数字にまだ興味がないみたいです。小学校入学までにできるようになりますか?
A1. はい、大丈夫です。
この時期の興味には個人差が大きいため、まだ興味がなくても心配いりません。
小学校入学までに大切なのは、読み書きや計算ができることそのものではなく、学びへの好奇心を持つことです。
買い物でおつりを数える、絵本を読み聞かせながら文字を指差すなど、遊びや生活の中で自然に文字や数に触れる機会を増やしてあげましょう。
親が焦らず、子どものペースに合わせて見守ることが一番大切です。
Q2. 共働きで平日はバタバタです。子どもと向き合う時間が少なくても大丈夫でしょうか?
A2. 量より質を意識することが重要です。
たとえ10分でも、テレビやスマートフォンを消して、子どもと目を合わせ、今日あった出来事を話したり、抱きしめたりする時間を作りましょう。
また、家事の一部を子どもと一緒に「ゲーム」として楽しむのもおすすめです。
例えば、「食器運びリレー」や「靴下ペア探し」など、短い時間でも一緒に何かを成し遂げる体験が、子どもの心を満たします。
Q3. 習い事はいつから始めるのがベストですか?周りの子はみんなやっています…
A3. 周りと比べる必要はありません。
習い事を始めるのに「ベストな年齢」はなく、一番大切なのはお子さんが「やってみたい!」と興味を持っているかどうかです。
まずは体験レッスンにいくつか行ってみて、お子さんがその習い事を心から楽しめるかどうか、先生との相性はどうかを確認しましょう。
もし、どうしても興味を持てないようなら、無理に始める必要はありません。
家庭での遊びや体験を重視するのも素晴らしい選択肢です。
Q4. 子どもがなかなか片づけをしてくれません。どうすれば習慣になりますか?
A4. 「片づけ」を「遊び」に変える工夫をしてみましょう。
おもちゃの場所を一緒に決め、「おもちゃさんのお家はここだよ」と声をかけたり、タイマーを使って「お片づけタイムアタック」をしたりするのも効果的です。
また、片づけは親が完璧にやるのではなく、「一緒にやる」姿勢が大切です。
最初は親が手伝い、少しずつ「ここから先は自分でできるかな?」と任せてみましょう。
Q5. 友達とケンカが多くて心配です。どう関わればいいですか?
A5. ケンカは、子どもが社会性を学ぶ大切な機会です。
親がすぐに仲裁に入るのではなく、まずは見守ってみましょう。
ケンカの後は、「何が嫌だった?」「どうしてそう思った?」と子どもの気持ちを丁寧に聞き、「次はどうすればよかったかな?」と一緒に考える時間を持ちましょう。
相手の気持ちを想像する練習をすることで、コミュニケーション能力が育ちます。
Q6. 小学校入学までに、ひらがなはどこまで読めて書けるようにすべきですか?
A6. 入学までに、自分の名前が読める、書ける程度のレベルで十分です。
小学校に入ってから、先生が丁寧に教えてくれます。
それよりも大切なのは、文字や言葉に親しみ、読んだり書いたりすることへの抵抗感がないことです。
絵本をたくさん読んであげたり、スーパーの看板の文字を一緒に読んだりするだけでも、子どもは自然と文字に興味を持つようになります。
Q7. 通信教育やワーク教材は、市販のドリルと何が違いますか?どれを選べばいいですか?
A7. 通信教育は、教材が毎月届くため学習習慣がつきやすく、親の教材選びの手間が省けます。一方、市販のドリルは、子どもの興味や進度に合わせて、親が自由に選べるのがメリットです。
どちらを選ぶにしても、お子さんが「楽しそう!」と感じて、1日5~10分で無理なく続けられるものを選ぶことが重要です。
まずは書店で中身をチェックしたり、体験版を試してみることをおすすめします。
まとめ|5歳児期の学びが「小1の壁」を軽くする
小学校入学を迎えると、多くの家庭が直面するのが「小1の壁」です。
これは、子どもが新しい環境に慣れるまでの不安や、保護者が仕事と子育てを両立する中で直面する困難を指します。
特に共働き家庭では、登下校の見守りや学童の利用、宿題への対応など、日々の生活に新しい課題が加わることで負担が増すことがあります。
しかし、5歳のうちに「からだ・ことば・こころ・生活」の土台を整えておけば、この壁はぐっと低くなります。
自分のことを自分でやる力、友だちと協力できる力、言葉で気持ちを伝える力は、学校生活をスムーズにする大きな助けとなります。
大切なのは、特別な準備ではなく毎日の積み重ね。
短い時間でできる学び、遊びを通じた体験、生活リズムを整える工夫など、忙しい家庭でも無理なく取り入れられる方法はたくさんあります。
ぜひ、この記事で紹介したヒントを参考に、お子さんの成長を温かくサポートしてください。
5歳の今だからこそできる小さな習慣が、入学後の安心と親子の笑顔につながります。