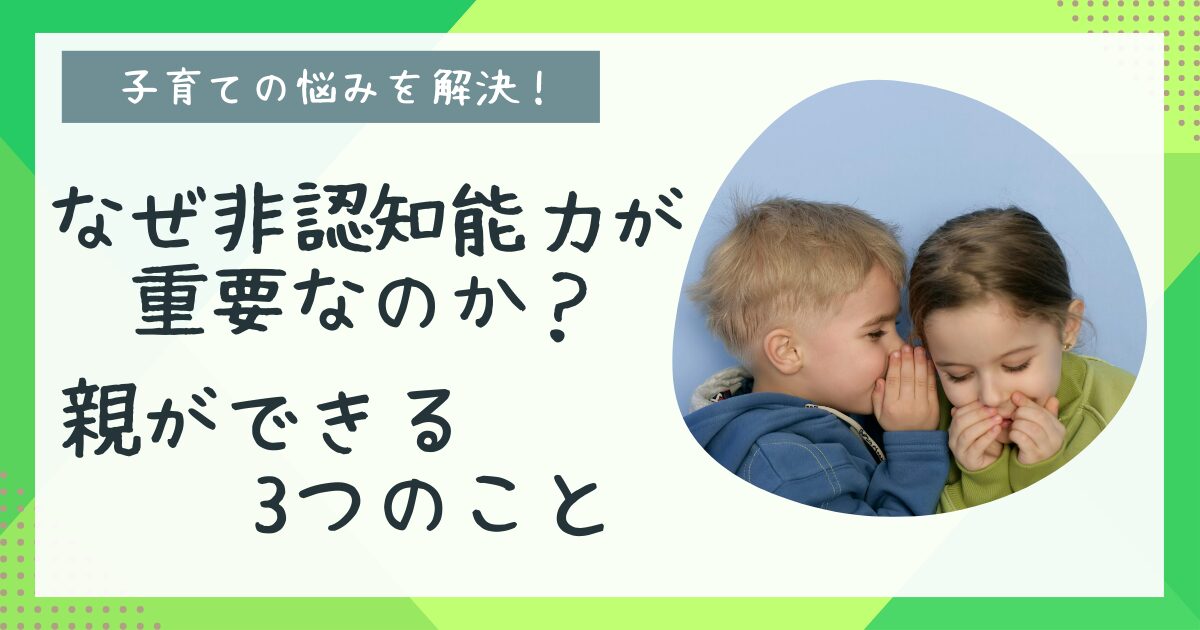
「うちの子、ゲームばかりで全然勉強しない…」
「友達とよくケンカするし、将来が不安…」
「ちょっと注意しただけで、すぐに癇癪を起こす…」
「新しいことに挑戦したがらず、すぐに諦めてしまう…」
子育てをしていると、こんな悩みは尽きませんよね。
「うちの子、大丈夫かな…?」と不安になることもあるでしょう。
でも、ちょっと待ってください。
実は、学力やテストの点数では測れない「非認知能力」が、子どもの将来を大きく左右することがわかっています。
この非認知能力を伸ばすことで、子どもは「困難を乗り越える力」や「自ら学ぶ力」を育み、将来の選択肢が広がります。
この記事では、非認知能力とは何か、なぜ重要なのか、そして親が今日からできる3つのことを具体的にご紹介します。
1. 非認知能力とは?なぜ今、重要なのか?

「認知能力」とは、IQや学力など、数値で測れる能力のこと。
一方、「非認知能力」とは、数値では測れない、生きるために必要な力のこと。
例えば、
- 自制心: 誘惑に打ち勝ち、目標に向かって努力する力
- 協調性: 友達と協力し、仲良くやっていく力
- 創造性: 新しいアイデアを生み出し、問題を解決する力
- 問題解決能力: 困難な状況を乗り越える力
などがあります。
「そんなの、当たり前じゃない?」
そう思ったあなたは、素晴らしい感性を持っています。
でも、なぜ今、非認知能力が重要視されているのでしょうか?
それは、社会の変化が激しいからです。
AIが発達し、グローバル化が進む現代社会では、「言われたことをこなす」だけでは生き残れません。
自ら考え、行動し、周りの人と協力しながら、新しい価値を生み出す力が必要なのです。
だからこそ、非認知能力が注目されているのです。
2. 非認知能力が重要な理由
「非認知能力って、本当に重要なの?」
そう思う方もいるかもしれません。
そこで、研究が示す非認知能力の重要性をご紹介します。
- ペリー幼児教育プログラム(アメリカ): 幼児期に「忍耐力・協調性・やり抜く力」を育てた子どもは、成人後の収入が高く、犯罪率が低かった
- 日本の研究(ベネッセ教育総合研究所): 非認知能力が高い子どもは、学力・人間関係・ストレス耐性が高い
自制心が高い人は、目標を達成しやすく、ストレスにも強い傾向があります。
協調性がある人は、周りの人と良好な関係を築き、協力して物事を進めることができます。
創造性がある人は、新しいアイデアを生み出し、変化に対応することができます。
このように、非認知能力は、人生の様々な側面において、重要な役割を果たしているのです。
つまり、学力だけではなく、人生全般において成功しやすくなるのが「非認知能力」なのです。
3. 親ができる3つのこと
① 土台を築く:「情緒の安定と安心感」

非認知能力を育むには、まず子どもが安心して挑戦できる「心の土台」をつくることが大切です。
✅ 今日からできる習慣
- 1日1回は「大好きだよ」「ありがとう」と伝える
- 子どもの話を最後まで聞く(途中で口を挟まない)
- 失敗を責めず、「どうすればうまくいくか?」を一緒に考える
例: おもちゃを壊してしまったとき
子ども: 「ママ、ごめんなさい…おもちゃが壊れちゃった…」
親: 「そっか、壊れちゃったんだね。どんなふうに壊れたの?」
子ども: 「うーん…強く引っ張ったらパキッて…」
親: 「そっか。じゃあ、どうしたらまた遊べるようになるかな?」
子ども: 「接着剤でくっつける?」
親: 「いいアイデアだね!一緒に直してみようか。でも、次からはどんなふうに扱えば壊れにくいかな?」
子ども: 「やさしく使う!」
親: 「そうだね!次から気をつけてみよう!」
➡ 「失敗=ダメ」ではなく、「どうすればいいか」を考える機会にすることで、問題解決能力や自制心を育む。
ポイント
親に認められていると感じると、子どもは自信を持ちやすくなります。
② 根っこを育む:「好奇心と探求心を刺激する」

好奇心が強い子どもは、自ら学ぶ力が育ちます。
✅ 今日からできる習慣
- 「なんで?」と聞かれたら、「どう思う?」と逆に質問する
- 本・図鑑・パズル・実験など、ワクワクする環境を用意する
- 動物園や科学館など、子どもが自由に考えられる体験を増やす
ポイント
「答えを教える」のではなく、「考える機会を増やす」ことが大事です。
③ 幹を太くする:「自立心とやり抜く力を育てる」

失敗してもへこたれず、粘り強く挑戦する力が非認知能力を育みます。
✅ 今日からできる習慣
- 子どもに役割を与える(料理、片付けなど)
- 小さな目標を一緒に決めて達成感を味わわせる
- 努力を具体的に褒める(「頑張ったね!」ではなく「毎日10分練習したね!」)
ポイント
「成功したこと」だけでなく、「努力した過程」を認めると、やり抜く力が育ちます。
4. よくある疑問と親の不安

Q. うちの子は人見知りですが、協調性を育むにはどうしたらいいですか?
A. まずは少人数で遊ぶ機会を作り、無理なく人と関わる場を増やしてみましょう。
例えば、近所の公園で遊んだり、児童館のイベントに参加したりするのも良いでしょう。
Q. 非認知能力は遺伝で決まるのでしょうか?
A. いいえ。非認知能力は環境や経験によって大きく育ちます。 親の関わり方次第で伸ばすことが可能です。
例えば、絵本の読み聞かせや、親子で一緒に遊ぶことでも、非認知能力を育むことができます。
5.まとめ:今日から1つ実践してみよう!
非認知能力は、子どもの将来にとって「学力以上に大切な力」です。
✅ 親ができる3つのこと
- 子どもを肯定し、安心できる環境を作る(情緒の安定)
- 子どもの好奇心を刺激し、「なぜ?」を大切にする(探求心)
- 成功体験を積み重ね、やり抜く力を育てる(自立心)
「全部やらなきゃ!」と思わなくて大丈夫です。
まずは、今日できることを1つだけ実践してみてください!
子どもは、親の小さな工夫の積み重ねで大きく成長します。
おすすめ記事 (非認知能力の育成シリーズ)
- 「なぜ非認知能力が重要なのか?親ができる3つのこと」(基本概念)→この記事
- 「遊びで伸ばす非認知能力|3歳からの簡単アクティビティ5選」(実践編)
- 「やる気を引き出す「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」の効果的な組み合わせ方」(モチベーション編)
- 「運動×非認知能力:子どものやる気を引き出す運動習慣の作り方」(運動分野)
- 「家庭でできる音楽教育と非認知能力の育成」(音楽分野)
- 「アート体験&鑑賞で子どもの才能開花!親子で育む非認知能力」(芸術分野)
- 「自然体験で非認知能力を伸ばす!親子で楽しめるアウトドア学習」(自然分野)