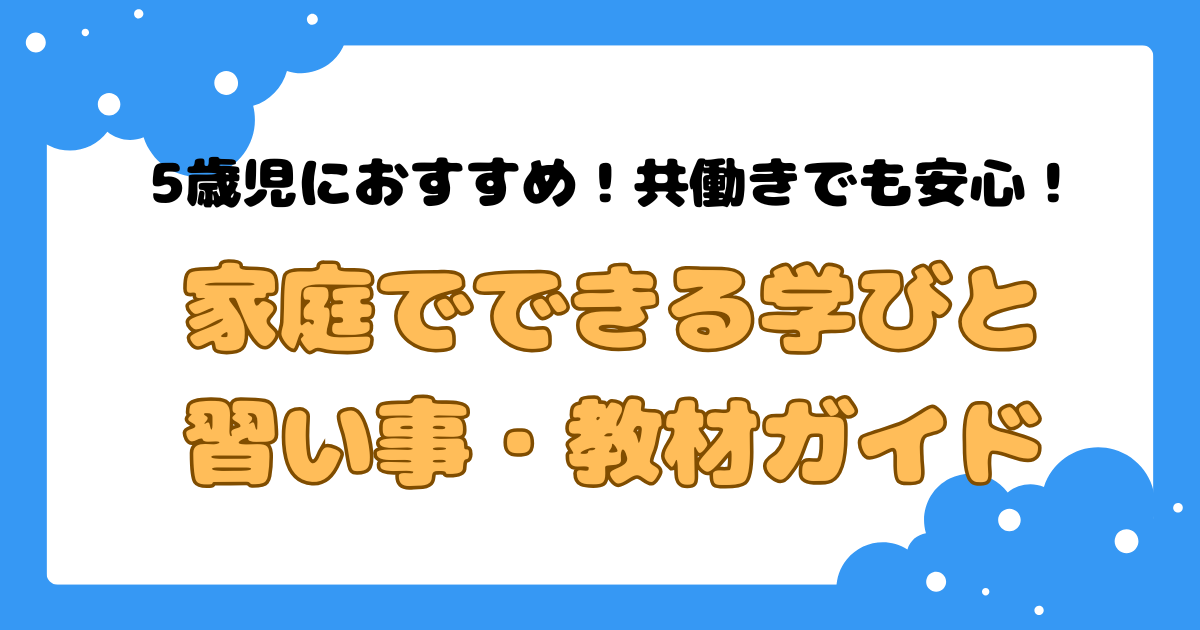
5歳になると「なんでも自分でやりたい!」という気持ちがますます強くなり、友だちとの関わりも深まってきます。
この時期は、身体やことばの発達が大きく伸びるタイミングであり、家庭での過ごし方や習い事・教材選びが子どもの成長に大きく影響します。
親としては、
✅「どんな習い事が向いているの?」
✅「教材って必要なの?」
✅「共働きでも続けられる方法はある?」
と悩んでいませんか?
この記事を読めば、その答えがきっと見つかります。
この記事でわかること
・5歳児の発達に合わせた習い事の選び方
・お金をかけずにできる、家庭での学びのヒント
・忙しい共働き家庭でも無理なく続けられる工夫
5歳児におすすめの習い事や教材の選び方、家庭でできる工夫、共働き家庭でも無理なく取り入れられる方法までをまとめました。
「やらせなきゃ」と焦るのではなく、「楽しみながら学べる」環境を整えるヒントを一緒に見ていきましょう。
1.5歳児に習い事や教材が必要な理由
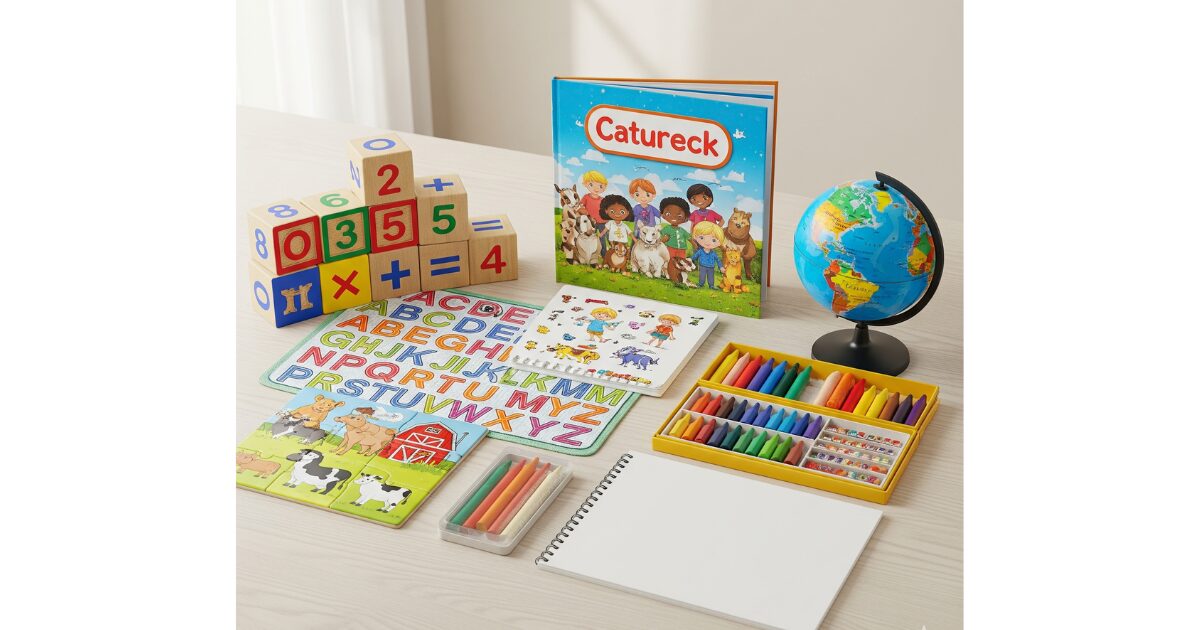
「5歳から習い事は早いのでは?」と思う親御さんもいれば、「小学校に入る前に少し準備をしておきたい」と考える方もいるでしょう。
実は5歳は、体・心・知識の面でぐんと伸びるタイミング。
家庭だけでは補いきれない刺激や経験を取り入れることで、子どもの可能性をさらに広げられます。
発達段階から見た5歳児の特徴
5歳児は、成長のスピードが一気に加速する年齢です。
運動能力
✅体幹やバランス感覚が安定し、片足立ちやスキップも上手にできるようになります。
👉リズムに合わせて体を動かすことも得意になり、運動系の習い事を始めやすい時期です。
言語能力
✅語彙がぐっと増え、会話の中で自分の気持ちや考えを表現できるようになります。
👉絵本の物語を理解して感想を言えたり、友だちとのやり取りがスムーズになったりと、言葉を使った学びが大きく伸びる時期です。
社会性
✅友だちと協力して遊んだり、ルールを守ろうとする意識が芽生え始めます。
👉集団の中での振る舞いを学ぶ絶好の機会であり、小学校生活につながる「社会の基礎力」が育ちます。
習い事や教材がもたらすメリット
このような発達の特徴をふまえると、習い事や教材が子どもに与えるメリットは大きいといえます。
体験を通じて「自信」や「達成感」を得られる
新しいことに挑戦し、できるようになる喜びは自己肯定感につながります。
家庭ではできない「先生・友だちとの関わり」が経験できる
習い事や学びの場は、異年齢や初めて会う大人との関わりを通じて、人間関係を広げるきっかけになります。
興味を広げ、小学校入学の土台づくりになる
文字や数、音楽や運動などの体験は、「勉強の先取り」ではなく、「学びを楽しむ姿勢」を育てる準備になります。
2.家庭で取り入れたい学びの習慣

習い事や教材も大切ですが、実は家庭でのちょっとした工夫こそが、子どもの成長を大きく支える力になります。
特別な時間を作らなくても、日常生活の中に学びを取り入れることができるのです。
👉 ここでは「生活・言葉・遊び」の3つに整理しました。どれも 特別な準備なしで今日から始められる家庭教育 です。
生活の中で育つ力
家庭での「お手伝い」や「お出かけ」など、何気ない日常の場面は、実は子どもにとって最高の学びのチャンスです。
大人にとっては当たり前のことでも、子どもにとっては新しい発見や挑戦の連続。
数や順序、社会のルールなどを自然に身につけられるのが魅力です。
お手伝い(料理・片づけ)で育つ数や順序の感覚
料理を一緒にすると、「にんじんを3つ切ってね」「お皿を4枚並べてね」と自然に数に触れることができます。
👉片づけも「大きい順に並べよう」と声をかけるだけで、分類や順序の感覚が育ちます。
買い物・外出で学ぶ社会性や数の理解
お金のやり取りを一緒に体験したり、道順を確認したりしましょう。
👉社会のルールや数字に親しむチャンスがたくさんあります。
会話・読み聞かせで伸びる言葉の力
5歳ごろは語彙がぐんと増え、物語を楽しむ力も育ってきます。
だからこそ、家庭での会話や絵本の読み聞かせが「言葉の力」を伸ばす絶好のタイミング。
親子のやりとりが豊かになるほど、表現力・想像力・聞く力がバランスよく育っていきます。
-
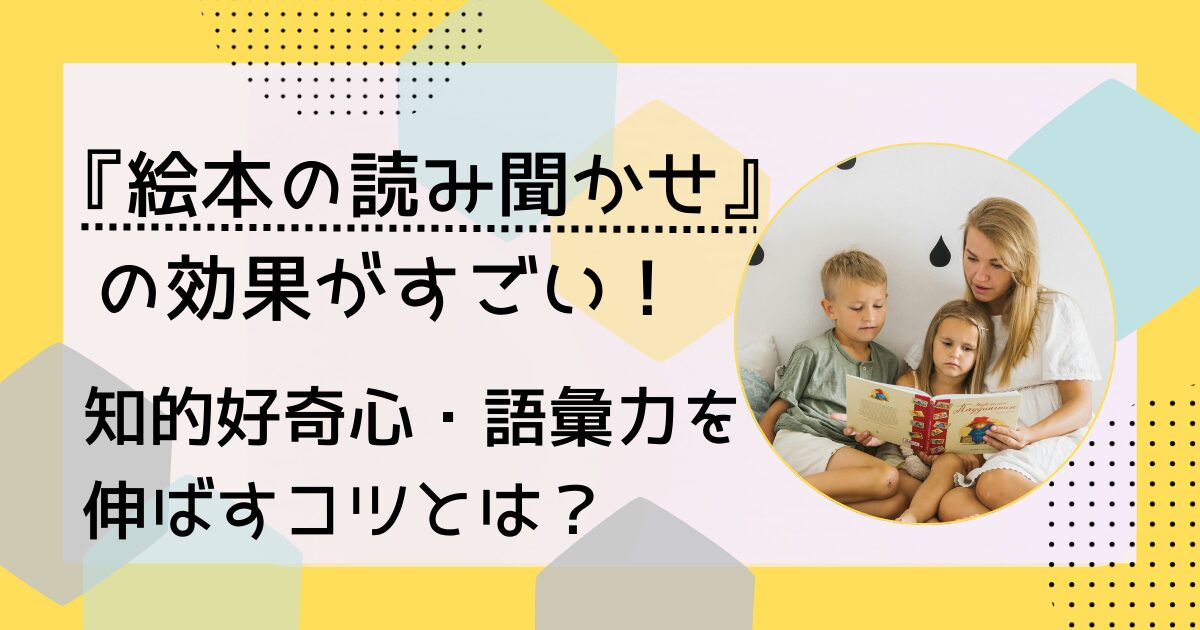
-
『絵本の読み聞かせ』の効果がすごい!知的好奇心・語彙力を伸ばすコツとは?
こんにちは、子育てに奮闘中の皆さん。 お子さんと過ごす時間の中で、「もっと成長を促してあげたい」「何 ...
続きを見る
絵本を一緒に読むことで「想像力」や「語彙」が増える
物語の続きを考えたり、「どうしてこうなったんだと思う?」と問いかけたりしましょう。
👉言葉だけでなく考える力も育ちます。
会話のキャッチボールで「表現力」「聞く力」が育つ
「今日楽しかったこと教えて」「どうやって遊んだの?」など、会話を広げる工夫をしましょう。
👉表現力と聞く力の両方が鍛えられます。
遊びを通じた学び
遊びは子どもにとって「学び」そのもの。
ブロックやごっこ遊びなど、一見ただの遊びに見える活動が、実は空間認知力や協調性をぐんと伸ばしてくれます。
楽しみながら自然に力が育つのが、遊びの大きな魅力です。
ブロック・パズルで「空間認知」や「問題解決力」
完成させるまでの試行錯誤が大切です。
👉集中力や粘り強さを育てます。
ごっこ遊びで「役割理解」や「協調性」
「お店屋さんごっこ」「病院ごっこ」なども魅力です。
👉ルールや役割を守る力を自然に学べる遊びです。
3.年齢・発達に合ったおすすめ習い事

ここでは、5歳児の発達に合ったおすすめの習い事を、そのメリットと合わせて一覧でまとめました。
| ジャンル | 習い事 | 期待できる効果 |
| 運動系 | 水泳 | ・基礎体力と心肺機能の向上 ・「泳げた!」という達成感が大きな自信に |
| 体操 | ・柔軟性、バランス感覚、体幹を鍛える ・ケガをしにくい体づくり | |
| サッカー・ダンス | ・仲間との協力で社会性を育む ・リズム感や協調性を養う | |
| 言語・学習系 | 英語 | ・耳が柔らかい時期に自然な発音を習得 ・歌やゲームで異文化に親しむ |
| ひらがな・カタカナ | ・遊び感覚で文字に親しむ ・読み書きへの抵抗感をなくす | |
| 算数準備(数遊び) | ・具体物を使ったゲームで数の感覚を養う ・小学校の算数への苦手意識をなくす | |
| 芸術・表現系 | 音楽(ピアノ・リトミック) | ・感受性や集中力を育てる ・音楽に合わせて体を動かし、表現力を伸ばす |
| 絵画・造形 | ・自己表現力や創造力を伸ばす ・自由に作る楽しさを知り、発想力を豊かにする |
5歳は「やってみたい!」という気持ちが強くなる時期。
習い事を始めるのにぴったりの年齢です。
大切なのは、「将来役立つかどうか」よりも「子どもが楽しく続けられるかどうか」 です。
👉 習い事は「できることを増やす」のが目的ではなく、子どもの世界を広げてあげるためのもの です。
家庭での学びと合わせることで、バランスよく力が育ちます。
4.家庭で使えるおすすめ教材・知育アイテム

習い事に通うのも良いですが、家庭でも「遊びながら学べる環境」を整えることが大切です。
毎日の生活に自然に取り入れられる教材や知育アイテムを紹介します。
👉 ポイントは、「教材=勉強」ではなく「遊びや生活に自然に溶け込むもの」 として取り入れること。
そうすることで、子どもが楽しく続けられます。
知育玩具
✅ブロック・レゴ:空間認識力や発想力を養う
「積む・組み合わせる・壊す」というシンプルな動きの中で、論理的思考や創造力が育ちます。親子で一緒に作るのもおすすめ。
✅パズル:集中力や論理的思考を鍛える
ピースをはめる過程で「形を見分ける力」「順序を考える力」が伸びます。完成したときの達成感も自信につながります。
ワーク教材
✅ドリル(ひらがな・数):1日5分で無理なく取り組める
長時間でなくてもOK。毎日短く積み重ねる習慣が大切です。文字や数に親しむ入り口として役立ちます。
✅書き方練習:入学準備にもつながる
正しい鉛筆の持ち方や線を書く練習をするだけで、小学校入学後の学習がスムーズになります。
デジタル教材
✅アプリや動画:楽しくインプットできる
歌やゲームを通して学べるデジタル教材は、子どもの好奇心を刺激する強力なツールです。
✅注意点:時間のルール設定・親の見守りが必要
デジタル教材は「使いすぎ」が一番のリスク。親が一緒に取り組んだり、利用時間を区切ったりしてバランスを取りましょう。
5.習い事・教材を選ぶときのポイント

子どもの成長を第一に考え、親も無理なく続けられるように、以下の3つのポイントを参考に選びましょう。
| ポイント | なぜ大切? | 具体的なチェックリスト |
| 子どもの興味 | 無理にやらせても効果は薄く、むしろ逆効果になることも。 子どもが「やってみたい!」と感じる習い事や、夢中になれる教材が一番大切です。 | ・体験レッスンで子どもの反応を見る ・普段どんな遊びに夢中になっているか観察する ・子どもに「どれが楽しそう?」と尋ねてみる |
| 続けやすさ | 素晴らしい習い事でも、送迎や費用が負担になると長続きしません。 親の負担も考慮した「無理のない範囲」が重要です。 | ・通いやすい場所か、送迎時間は確保できるか ・家計に無理のない費用か ・教材は片付けやすいか、サポートは大変ではないか |
| 親の関わり方 | 子ども任せにせず、一緒に楽しむ姿勢が子どものモチベーションを上げます。 | ・送り迎えの車内でも「今日はどうだった?」と会話する ・教材を一緒に開けて、「これやってみようか」と誘う ・子どもが楽しんでいる部分を具体的に褒める |
習い事や教材は数多くありますが、すべてが子どもに合うわけではありません。
選ぶ際には、「何から手をつければいいか分からない」と感じるかもしれません。
大切なのは「続けられるか」「子どもが楽しめるか」。
👉 習い事も教材も「子どもが楽しみながら、親も無理なく関われる」ことが選ぶときの大事な基準です。
6.忙しい共働き家庭でも続けられる工夫

共働き家庭では、習い事や教材の時間をどう確保するかが大きな課題です。
以下の表を参考に、無理なく続く仕組みづくりを始めましょう。
| タイプの工夫 | 具体的なアイデア例 | メリット |
| スキマ時間の活用 | ・朝の10分で読み聞かせや言葉遊び ・夜の5分で「今日の楽しかったこと」を聞く ・移動中に知育アプリや動画を活用 | ・特別な時間を作らなくていい ・毎日続けることで習慣化しやすい ・子どもの語彙力や表現力が自然に育つ |
| 週末の集中学習 | ・土日だけ通う習い事や体験型イベントに参加 ・図書館や博物館など、知的好奇心を満たすお出かけ ・週末にまとめて家庭学習に取り組む | ・平日の負担を減らせる ・親子でじっくり向き合える時間が増える ・非日常の体験で子どもの興味が広がる |
| 家事を学びの場に | ・調理を「算数」と結びつける(例:にんじんを3本切る) ・片付けを「ルール遊び」にする(例:車を赤い箱に戻す) ・配膳や洗濯物係など、小さな役割を与える | ・親子のコミュニケーションが増える |
ポイントは「短時間でも質の高い学びを取り入れる」「家庭でのサポートと組み合わせる」ことです。
特別な時間を無理に作るのではなく、日々の生活に自然に溶け込ませることが成功の鍵です。
7.よくある質問(FAQ)

ここでは、5歳児の習い事や教材について、よくある質問にお答えします。
どんな小さな疑問でも、子どもの成長にとっては大切なヒントです。
あなたが抱える疑問を解消し、前向きな一歩を踏み出すための参考にしてください。
Q1: 5歳児に習い事はまだ早いですか?
A: 5歳は「自分でやりたい」という意欲が高まる時期です。
⭐短時間で楽しめる内容なら、無理なく始められます。
Q2: 習い事は何種類もやらせたほうがいいですか?
A: 多すぎると負担になるため、1〜2種類に絞りましょう。
⭐習い事で学んだことを家庭の遊びや会話に広げてあげると、効果がぐんと高まります。
Q3: 家庭でできる学びはどんなことがありますか?
A: 読み聞かせや会話、お手伝い、買い物などがあります。
⭐買い物で『どっちが大きいかな?』と比べっこするなど、日常生活の中で自然に力を育む方法があります。
Q4: 習い事や教材はどのように選べばいいですか?
A: 子どもの興味や性格、家庭の生活リズムに合ったものを選ぶことが大切です。
⭐楽しめるかどうかもポイントです。
Q5: デジタル教材は使ってもいいですか?
A: はい。短時間でも楽しく学べたり、移動時間を有効活用できるのが利点です。
ただし、時間のルールや親の見守りを設定しましょう。
⭐家庭学習や遊びとバランスを取ることが大切です。
Q6: 共働き家庭でも続けられる方法はありますか?
A: 朝や夜のスキマ時間、週末の習い事などの工夫次第で無理なく続けられます。
自宅でできる教材(ワークや知育アプリ)や週末だけの習い事(水泳や音楽)などを選ぶと続けやすいです。
⭐無理に詰め込まず、1〜2種類に絞り、家庭での学びと組み合わせると負担が少なくなります。
Q7: 習い事や教材は小学校入学の準備に役立ちますか?
A: きっと役に立ちます。
⭐5歳児期に育てた運動能力・言語能力・社会性は、入学後の学びや生活に自信を持つ土台になります。
まとめ|5歳児の習い事・教材で育む力
この記事では、5歳児期に育むべき力と、それを支える習い事・教材の選び方、そして家庭でできる工夫を解説しました。
5歳児期は、運動能力・言語能力・社会性が大きく伸びる時期です。
この時期に習い事や教材を上手に取り入れることで、以下のような力が育ちます。
- 自信・達成感:体験を通じて自分でできた喜びを感じる
- 社会性:先生や友だちとの関わりを通じて協力やルールを学ぶ
- 興味の幅:運動・学習・表現の多様な体験で好奇心を広げる
家庭での学びも組み合わせることで、さらに効果が高まります。
例えば、読み聞かせや会話で言葉の力を育てたり、お手伝いや買い物で社会性や数の感覚を伸ばしたりすることができます。
共働き家庭でも、スキマ時間や週末を活用し、習い事と家庭学習をバランスよく取り入れることで、無理なく続けられます。
大切なのは、「楽しむこと」「少しずつ習慣化すること」。
5歳児期に身につけた基礎力は、小学校入学後の学びや生活の自信につながります。
この記事で紹介したアイデアを参考に、お子さんの成長を温かく見守りながら、家庭でのサポートを楽しんでください。