
「そろそろトイレトレーニングを始めたほうがいいのかな…?」
「他の子はもうパンツなのに、うちの子はまだおむつで大丈夫?」
子育ての中で、多くの親が頭を悩ませるテーマ、それがトイレトレーニング、つまり「おむつはずれ」ですよね。
進め方がわからない、始めるタイミングに迷う、途中で急に嫌がるようになった――そんなママ・パパのリアルな声、私たちも本当によく聞きます。
でも、どうか安心してください。
この記事は、トイレトレーニングを「ただのおむつはずし」として捉えるのではなく、お子さんの発達、心、そして文化的な背景にも触れながら、多角的に解説していきます。
忙しいパパママでもすぐに実践できる具体的なヒントや声かけの工夫、さらには「もしも」の時につまずかずに乗り越える対処法まで、ぎゅっと詰め込みました。
さあ、トイレトレーニングを、お子さんの「できた!」という喜び、そして「親子のかけがえのない成長のプロセス」として、一緒に楽しみませんか?
トイレトレーニングって何?「おむつはずれ」との違いを知ろう

「トイレトレーニング」という言葉を聞くと、「おむつを外すための訓練」や「厳しくしつけること」と構えてしまう方もいるかもしれません。
でも本来、トイレトレーニングとは、「子どもが排泄を自分で認識し、自立していく過程を、親が温かくサポートすること」を意味します。
つまり、単に「おむつが外れたかどうか」がゴールではありません。
お子さんが自分の身体の感覚や意思を理解し、それを行動につなげていく、その大切な「プロセス」なのです。
「おむつはずれ」と「トイレトレーニング」の違い、明確に!
よく似た言葉に「おむつはずれ」がありますが、これはどちらかというと結果を表す言葉。
トイレトレーニング:
親子で一緒に取り組む「学び」や「経験」のプロセス
おむつはずれ:
トイレで排泄できるようになった「状態」や「結果」
どちらも大切ですが、子どもの成長に寄り添うためには、結果だけを焦らず、「プロセス」に注目することがカギ。
焦って結果を求めすぎると、お子さんに余計なプレッシャーをかけてしまい、逆効果になることもあるんですよ。
トイレトレーニングの歴史と「今」のスタンダード
「昔はもっと早かったって聞くけど…?」
「みんな何歳くらいでしてるの?」
トイレトレーニングの考え方や進め方は、時代や文化によって大きく変化してきました。
まずはその背景を知っておきましょう。
20世紀初頭は「厳しく、早く!」
1900年代前半、特に西洋社会では、生後8ヶ月頃にはトレーニングを完了させるのが「当たり前」とされていました。
時には、強制的な手段や、現代では眉をひそめられるような方法が推奨されることも。
これは、子どもに規律と服従を植え付けるという当時の育児観や、布おむつの手間を減らしたいという実用的な動機付けが背景にありました。
「子ども中心」のアプローチへ大転換!
1940年代頃から、小児心理学の発展とともに、育児のアドバイスは大きく変わります。
ベンジャミン・スポック博士のような著名な小児科医が「子ども中心」の育児を提唱。
「親は子どもの手がかりを観察し、それに応える柔軟なアプローチを」と推奨されるようになりました。
これにより、トイレトレーニングの開始年齢は1歳半頃へと延び、個々の子どもの準備性が重視されるように。
プレッシャーを与えず、できたことを褒める「肯定的強化」の重要性が強調され、この考え方は世界的に広まりました。
紙おむつの普及がもたらした「ゆとり」と「変化」
20世紀後半、特に1970年代以降の使い捨て紙おむつの普及は、育児に革命をもたらしました。
安価で便利になったことで、親がおむつを早く外す動機は薄れ、トイレトレーニングの開始時期はさらに遅れる傾向に。
日本では、昭和30年頃の1歳半から、現在では平均3歳後半まで完了時期が遅延しているというデータもあります。
この「ゆとり」は、親子のストレス軽減につながる一方で、年間約300kgの廃棄物が発生するといわれている環境問題や、経済的負担という新たな課題も生み出しています。
世界を見れば「いろいろなやり方」!
トイレトレーニングの方法や時期、文化的ニュアンスは世界中で大きく異なります。
例えば、中国では生後数ヶ月という非常に早い時期からトレーニングが始まり、「股割れパンツ」の使用が一般的。
これは「早期のトレーニングが衛生と自立を促進する」という信念に基づいています。
布おむつが主流のインドでは、生後間もない赤ちゃんがおしっこやうんちのサインを出したら、特定の場所に抱きかかえる習慣も。
このように、トイレトレーニングは、その時々の育児観、社会経済的状況、科学的知見、そして文化が複雑に絡み合って変化していることを知っておくのは、私たち親にとっても大切な視点です。
いつから始める?わが子の「準備できたよサイン」を見逃さないで!

「何歳から始めればいいんだろう?」と気になるところですが、年齢や月齢だけで判断するのはNGです。
トイレトレーニングの成功は、お子さんの心と体の準備が整っているかに大きく左右されます。
無理に早く始めてしまうと、お互いにストレスになることも。
トイレトレーニング完了の平均年齢と、知っておきたい「個人の差」
お子さんの成長は一人ひとり違います。
トイレトレーニングが完了する時期も、お子さんによって本当にさまざまなので、焦らず、お子さんのペースを一番に考えてあげることが何より大切です。
昼間のおむつはずれは「3歳」が最も多い目安
日本の調査では、昼間のおむつが完全に外れるのは「3歳」というお子さんが最も多い傾向にあります。
しかし、これはあくまで「最も多い」時期であり、例えば2歳代で早くに完了するお子さんもいれば、4歳や小学校に入るまで時間がかかるお子さんもたくさんいます。
周りのお子さんと比べて「うちの子は遅いかも…」と心配になることもあるかもしれませんが、どうか安心してください。
夜間のおむつはずれは、さらに時間がかかることも
夜間のおむつ外しは、昼間よりもさらに時間がかかることが多いです。
3歳で夜間も完全に外れるお子さんは約3割程度といわれており、5歳を過ぎても夜間のおむつが必要なお子さんも珍しくありません。
これは、寝ている間の排泄コントロールが、昼間とは異なる発達段階を必要とするためです。
膀胱に尿を多く溜められるようになることや、睡眠中に尿の生成量を減らすホルモンがしっかり分泌されること、そして尿意で目が覚める能力が発達するには、さらに時間がかかります。
大切なのは、周りの子と比べることではなく、目の前のお子さんの「準備ができたよサイン」を見つけてあげることです。
【要チェック!】トイレトレーニング開始の「発達サイン」
以下のようなサインがいくつか見られ始めたら、トイレトレーニングを始めてみる良いタイミングかもしれません。
| 発達のサイン | チェックポイント | おおよその年齢目安 |
|---|---|---|
| 身体の発達 | ・数時間おしっこが出ない時間がある(膀胱にためられる証拠) ・おしっこの前に落ち着かなくなるなど、何らかのサインがある | 1歳半〜3歳 |
| 言葉の理解 | ・「ちっち」「でた」「トイレ」など、排泄に関する簡単な言葉のやりとりができる | 1歳半〜2歳 |
| 行動の自立 | ・簡単なズボンやパンツの上げ下げができる | 2歳〜3歳 |
| 興味・関心 | ・トイレやパンツに興味を持つようになる ・親や兄弟がトイレに行く様子をまねしたがる ・濡れたおむつを嫌がるようになる | 2歳〜3歳 |
お子さんによって個人差がとても大きいので、年齢はあくまで目安です。
焦らず、お子さんの様子をじっくり観察してあげてくださいね。
親の「心の準備」と「環境」も重要!

お子さんの準備がOKでも、親御さんの心や時間に余裕がなければ、うまくいかないこともあります。
忙しい時期は避ける:
引っ越し、下の子の出産、入園前など、生活が大きく変化する時期は、お子さんもストレスを感じやすいので避けるのがベター。
親がゆったり構えられるタイミングを選ぶ:
「今なら見守る時間があるな」と思える時期を選びましょう。
失敗してもOK!という心の余裕を持つ:
「完璧にこなさなければ」と気負いすぎると、親も子も疲れてしまいます。
「失敗は学びのチャンス!」と割り切るくらいの気持ちが大切です。
トイレトレーニングは、お子さんの発達と親御さんの環境がうまくかみ合った「タイミング」が何より大切です。
トイレトレーニングの3つの基本スタイルと4つのステップ
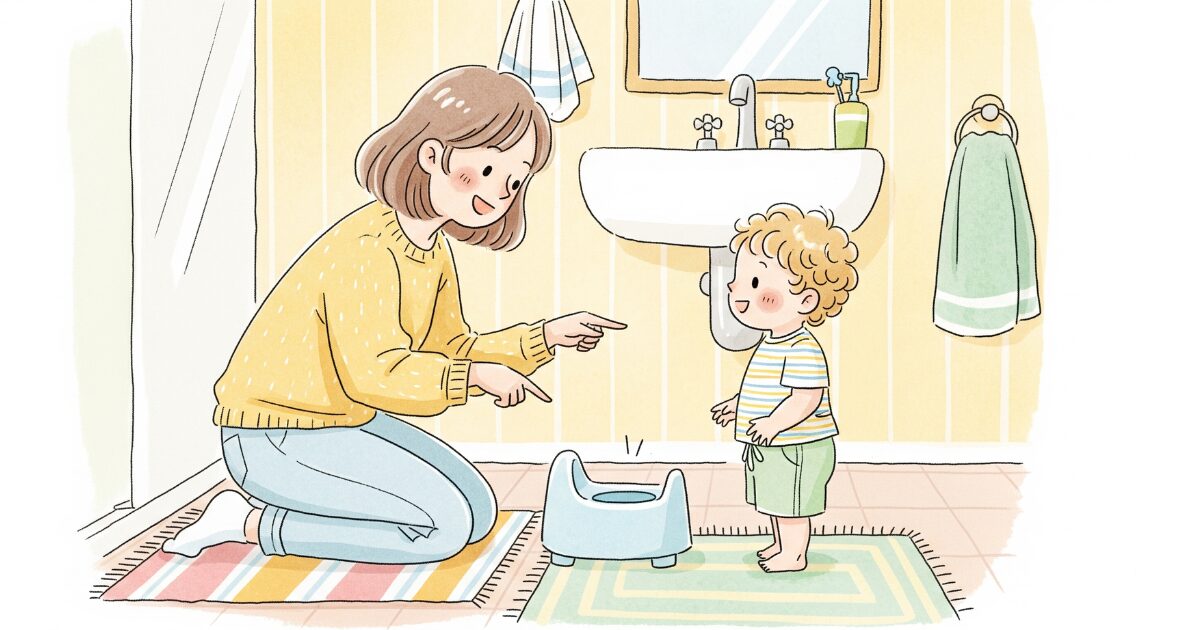
トイレトレーニングと一口に言っても、ご家庭によってやり方はさまざまです。
ここでは、代表的な3つの基本スタイルと4つのステップをご紹介します。
トイレトレーニング:3つの基本スタイル
1.【王道】トイレ誘導型
親が意識的に「トイレに行くタイミング」を誘導して、徐々に習慣化していく方法です。
特徴: 比較的オーソドックスで取り組みやすい。親子のコミュニケーションをとりながら進めやすい。
おすすめの家庭: 初めてトイレトレーニングに挑戦するご家庭や、比較的時間に余裕がある方。
2.【ゆるっと】布パンツ慣らし型
日中だけおむつを外して、布パンツやトレーニングパンツを履かせてみる方法です。
特徴: 「濡れて気持ち悪い」という感覚から、お子さんが排泄を意識できる。失敗も学びに変える前提で、ゆるくスタートできる。
おすすめの家庭: おうちで過ごす時間が多い日や、ゆったり見守れる環境のときに。
3.【短期集中】一気に外す型
おむつを一気にやめて、パンツ生活に切り替える集中スタイル。数日〜1週間程度で覚えさせることを目指します。
特徴: 成功すれば短期間で習得できる。
おすすめの家庭: 数日間、親がしっかりサポートできる時間が確保できる時期に向いています(ゴールデンウィークなどの連休を活用する家庭も多いです)。親の覚悟と準備が必須です。
トイレトレーニングの4つのステップ:焦らず段階的に進めよう!
トレーニングは次のようなステップで進めるとスムーズです。
ステップ1:トイレや排泄に興味を持たせる
✅トイレの絵本を一緒に読む
👉人気のトイレの絵本:ノンタンおしっこ しーしーやモンテッソーリのせいかつえほん トイレでできた
✅親がトイレに行く様子を見せる(「ママもおしっこしてくるね~」など)
✅おまるや補助便座に座る練習から始める(おしっこが出なくても「座れたね!」でOK)
👉おまる・便座 Amazonベストセラー1位
ステップ2:トイレに誘ってみる
✅起床後、食後、外遊び後など、排泄しやすいタイミングで積極的に誘う
✅無理やり連れていかず、「トイレ行ってみようか~」と優しく声かけ
ステップ3:パンツに挑戦する
✅トレーニングパンツや布パンツで“濡れる感覚”を体験させる
👉おすすめトレーニングパンツ:【MooMoo Baby】6層防漏構造トイレトレーニングパンツ女の子 男の子用
✅失敗しても絶対に叱らず、「次はトイレでできるといいね」と前向きに声かけ
ステップ4:成功体験を積む
✅成功したら思いきり褒める!ハグやハイタッチも効果的
✅シール帳やごほうびカレンダーを活用しても◎
👉人気ごほうびシール:トミカ & すみっコぐらし
トイレトレーニングにおける「なぜ?」を深掘り:おしっことうんち、昼と夜の違い

トイレトレーニングの過程では、おしっこ(排尿)と、うんち(排便)、そして昼間と夜間のおむつ外しにおいて、発達のメカニズムや完了時期に違いがあることが、専門的な研究でも指摘されています。
排尿と排便の自立、どっちが先?
多くの研究が、排便の自立の方が排尿の自立よりも早く達成される傾向があることを示唆しています。
うんちのコントロールは比較的早期に
排便のコントロールは、排尿よりも比較的早期に発達すると考えられています。
これは、排便の方が生理的な感覚がよりはっきりしており、排便前には体勢の変化や顔の表情など、お子さん自身や周りの大人が気づきやすいサインを出すことが多いからだとされます。
また、うんちの頻度やタイミングが、おしっこよりも予測しやすいという側面もあります。
便秘は要注意!
排便の自立においては、便秘が大きな課題となることがあります。
便秘によって排便時に痛みを感じると、お子さんが排便を我慢するようになり、さらに便秘が悪化するという悪循環に陥る可能性があります。
これは、お子さんのトイレトレーニングを妨げる大きな要因となることが指摘されています。
昼間と夜間のおむつ外しの違いって?
専門的には、昼間のおむつ外しが先行し、夜間のおむつ外しは遅れて達成されるのが一般的であると認識されています。
昼間の排泄自立は「意識的なコントロール」が鍵 !
昼間の排泄自立は、お子さんが起きている間に膀胱に尿を溜める能力、尿意を認識する能力、そしてトイレまで移動して排泄をコントロールする認知的・運動的能力が発達することで達成されます。
つまり、お子さんの意識的なコントロールが主体となります。
夜間の排泄自立は「体の発達」が重要 !
夜間の排泄自立(夜におねしょがない状態)は、昼間のコントロールとは異なる生理的メカニズムが関係しています。
睡眠中に膀胱が尿をより多く溜められるようになること(膀胱容量の増大)と、睡眠中に尿の生成量を減らすホルモン(抗利尿ホルモン)の分泌が増えること、そして尿意で目が覚める能力が鍵となります。
これらの機能が十分に発達するには、昼間の排泄自立よりも時間がかかるため、夜間のおむつ外しは遅れる傾向にあります。
これってどうする?よくある課題と対処法

トイレトレーニング中には、いくつか困ったことが起こるかもしれません。
そんな時も、落ち着いて対処できるよう、よくある課題と対応策を知っておきましょう。
おしっこやうんちのトラブル(便秘、おもらし、夜のおねしょ)
特に便秘は注意が必要です。
うんちを我慢すると便が硬くなり、出すときに痛くてさらに我慢してしまうという悪循環に陥ることがあります。
便秘がおねしょの原因になることもあります。
対処法:
・まずは小児科の先生に相談して、体の病気がないか確認しましょう。
・問題なければ、水分をこまめに摂る、食物繊維の多い食事を心がける、毎日決まった時間にトイレに行く習慣をつける、などの生活習慣の改善が大切です。
・夜のおねしょには、寝る2〜3時間前からの水分制限も有効です。
トイレを嫌がる、おもらしが増える
引っ越しや兄弟が生まれたなどの環境の変化、発達の遅れ、過去の排便時の痛みなどが原因で、トイレを嫌がることがあります。
対処法:
・失敗しても絶対に叱らないことが最も重要です。
・お子さんがストレスを感じているサインかもしれません。
・もし、不安や抵抗が強いようであれば、専門家(心理療法士など)に相談することも検討してください。
👉おすすめ防水シーツ:Amazonベストセラー1位おねしょシーツ(丸洗い&乾燥機OK)
👉おすすめおねしょ対策パット:ピジョン オムツ とれっぴ~ おねしょ対策パット(夜用) 24枚入
発達に特性があるお子さんの場合
自閉スペクトラム症(ASD)やADHDなど、発達に特性があるお子さんは、トイレトレーニングに時間がかかったり、特別な配慮が必要になったりすることがあります。
例:
- 感覚の苦手: トイレの音や匂い、便座の感触が苦手なことがあります。
- こだわりの強さ: 決まった場所や方法でしか排泄できないことがあります。
- 体のコントロールの難しさ: 尿意や便意に気づきにくかったり、力を入れるのが苦手だったりすることがあります。
対処法:
・環境を整えたり、感覚に慣れる練習をしたり、スモールステップで根気強く取り組むことが大切です。
・早めに作業療法士や発達小児科医などの専門家に相談し、お子さんに合った支援計画を立ててもらいましょう。
親御さんのストレス
「いつから始めるべきか分からない」「子どもが意思表示してくれない」など、親御さんも悩みを抱えることが多いです。
対処法:
・焦らず、お子さんのペースを尊重する気持ちが大切です。
・子育て支援センターや地域の保健センターなど、専門機関に相談することも助けになります。
・一人で抱え込まず、周りの人に頼ることも重要です。
保育園・幼稚園との連携のコツ|家庭との“チームプレー”で進めよう!

トイレトレーニングをスムーズに進めるためには、家庭と園の連携がとても重要です。
園と上手に協力し合うことで、お子さんも安心して取り組めるようになります。
トレーニングの“進み具合”を共有しよう
家庭でどこまで進んでいるか、またお子さんがどんな様子かを担任の先生に伝えると、園でもそれに合わせた対応がしやすくなります。
例:
「トイレに座る練習をしています」
「おしっこの間隔は2時間くらいです」
「まだうんちはオムツの中が安心みたいです」
👉連絡帳に簡単にメモするだけでもOK!
保育園側のやり方も聞いてみよう
園ごとにトレーニングの方針や進め方が違うこともあります。
例えば…
決まった時間にトイレに誘っている園
お友達と一緒に楽しく取り組んでいる園
オムツ外しの目標時期がある園 など。
👉それを知ることで、家庭での対応も一貫性が生まれ、お子さんが混乱しにくくなります。
着替えやトレパンは多めに準備
トイレトレーニング中は、失敗はつきもの。
保育園に預ける際にはトレーニングパンツや着替えを多めに持たせておきましょう。
👉先生も「たくさんあると助かります!」とよく言われます。
成功体験を家庭でも園でも喜び合う
園で初めて成功した日や、自宅でトイレに行けた日など、嬉しい出来事はぜひ共有を!
家で「保育園でできたんだって?すごいね!」と褒める
園で「おうちでできたって聞いたよ!えらいね」と声をかけてもらう
👉このダブルで喜んでもらえる経験”が、お子さんの自信になります。
一緒に悩める“味方”として相談を
「うちの子、進みが遅いかも…」「うんちだけどうしてもトイレでできない」など、困った時は一人で抱え込まず、遠慮なく先生に相談してみましょう。
保育のプロだからこそ、家庭では気づかない視点でアドバイスしてくれることも多いです。
👉「一緒に育てていく」チームとして関わる気持ちが大切です。
トイレトレーニングを“学び”に変える|成功・失敗の積み重ねが育てる力とは

トイレトレーニングは、単なる生活習慣の習得にとどまりません。
実はこの経験を通して、子どもは非認知能力(自己肯定感・自立心・粘り強さなど)を自然と育んでいきます。
併せて読みたい
子どもの自己肯定感を段階的に高めるためのステップはこちら
👉【 【子育ての悩みを解決】子どもの自己肯定感を高める3つのステップ|親ができること 】
成功体験=「やればできる!」の自己肯定感に
はじめは失敗していた子も、「トイレでできた!」という経験を積み重ねることで、「ぼく、できた!」「わたし、えらいでしょ!」と達成感を感じ、自信が育っていきます。
👉小さな成功体験の積み重ねは、のちの学びにもつながる“土台”です。
失敗しても大丈夫!「大人がどう受け止めるか」が大事
おもらしをした時や、トイレに間に合わなかった時に、叱るのではなく
「次は大丈夫だよ」
「気づけたの、えらいね」
「ちゃんと教えてくれてありがとう」
👉前向きな言葉をかけることで、失敗から学ぶ力(レジリエンス)が育ちます。
自分でできるようになる=自立への一歩
ズボンを脱いでトイレに座る、終わったら流す、手を洗う…この一連の流れを少しずつ自分でできるようになることは、“自立の第一歩”です。
👉親が手を貸しすぎず、「見守る勇気」を持つことも大切です。
「一緒に乗り越えた」経験は親子の絆に
うまくいかない日も、がんばった日も、全部ひっくるめて親子で体験したトイレトレーニングの時間は、信頼関係を深める貴重な時間になります。
👉だからこそ、焦らず、比べず、わが子のペースを大切に。
大切なのは、親も“成長する姿”を見せること
子どもは大人の姿をよく見ています。
「うまくいかない時にどうするか」
「困った時にどう考えるか」
👉それを親自身がトイレトレーニングを通して見せることが、何よりの教育です。
まとめ|トイレトレーニングは“親子の成長物語”
トイレトレーニングは、子どもが成長する過程のひとつであると同時に、親にとっても「見守る力・支える力・信じる力」を育てる貴重な機会です。
焦らず、比べず、お子さんのペースに寄り添いながら…。
その日々の積み重ねが、きっと親子のかけがえのない思い出になります。
もし、今トイレトレーニングで悩んでいることがあれば、どんなことでも一人で抱え込まず、専門家や地域の相談窓口に気軽に相談してみてくださいね。