
「あの先生、いつも優しいよね」から始まる信頼。
保育園から帰ってきた子どもが「先生ね、今日も一緒におままごとしたんだよ!」と嬉しそうに話してくれたこと、ありませんか?
保育士さんの声かけや接し方ひとつで、子どもの心は驚くほど変化します。
親としても、「どんな先生に見てもらえるか」は大きな関心ごとのひとつ。
けれど、保育者の関わり方は数値化しにくく、見学だけではなかなか分かりづらいのも事実です。
そこで注目したいのが「ECERS(エカーズ)」という国際的な保育環境評価スケール。
この評価項目には、保育者の関わり方を丁寧に見る視点が盛り込まれています。
この記事では、
「ECERSではどんな保育者の関わり方が“質が高い”とされるのか?」
「それが子どもや親にどう影響するのか?」を、
保護者目線でわかりやすくお伝えします。
🧭 ECERS実践編シリーズ|親が学ぶ保育の質
◀️前のステップ:
【保育園選びの決定版】ECERS-3で後悔しない園を見つける!親が知るべきチェックポイント
└ 質の高い保育を提供している園を客観的に見極める方法をわかりやすく解説。
▶️次のステップ:
保育園でも家庭でも|ECERSが教える子どものための“安全と健康”の整え方
└ ECERSの視点から、保育園チェックポイントとや家庭できる実践的な工夫を解説
ECERSが評価する「保育者の関わり方」とは?

ECERSには「人的環境(Interaction)」というカテゴリがあり、ここで保育者と子どもの関係性が重点的に評価されます。
評価の視点は、たとえば以下のようなもの:
- ✅子どもが安心して甘えられる関係が築かれているか
- ✅保育士が子どもの話をしっかり聞き、肯定的に受け止めているか
- ✅遊びや活動の中で、保育者が対話を通じて関わっているか
- ✅子ども同士のトラブル時に、保育者が仲裁するだけでなく、子ども自身の気持ちや考えに寄り添っているか
ポイントは「ただ見守る」のではなく、「適切な距離で、積極的に関わる姿勢」が求められること。
ECERSでは、こうした日常の中での保育者のふるまいが、子どもの情緒的な安定や社会性の発達にどう影響しているかを丁寧に観察・評価します。
子どもの心を育てる関わり方とは?|親が見学で注目したい視点
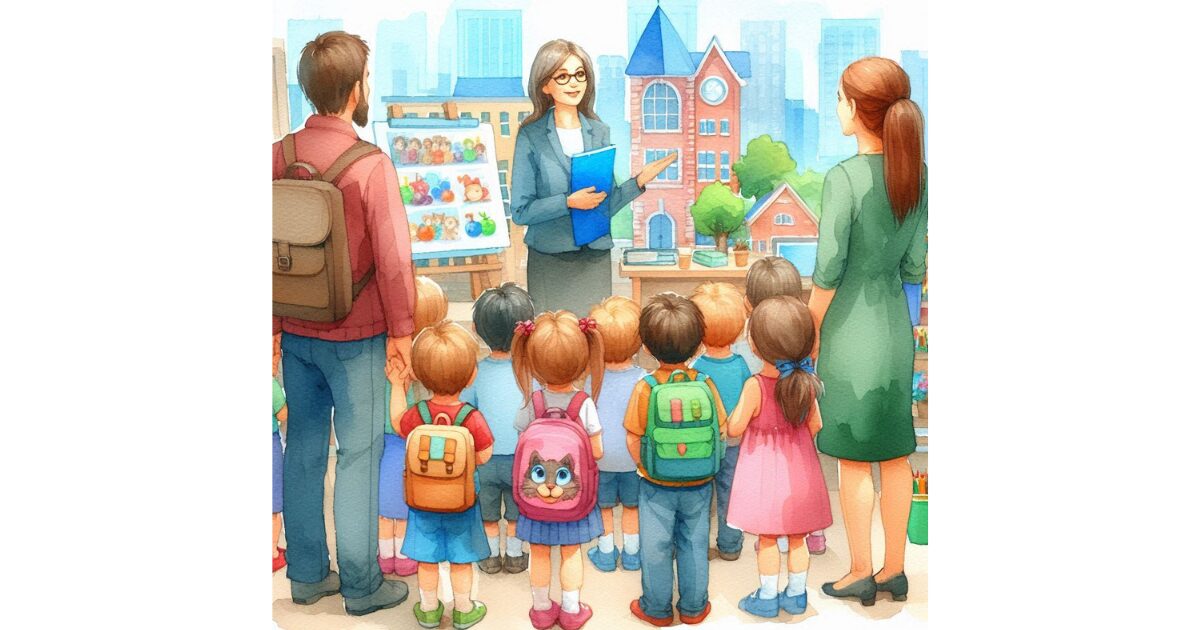
では、保護者が園見学などで確認できる「関わり方」のポイントには、どんなものがあるでしょうか?
✅ 子どもへの声かけに『名前』が入っているか
「ちゃんと座ってね」ではなく「〇〇ちゃん、座ってくれてありがとう」
名前を呼んでもらえるだけで、子どもは“私を見てくれてる”と感じ、安心感につながります。
✅ 保育者の視線が子どもに向いているか
常に子どもの行動に目を配り、声をかけたり、必要なときにそっと寄り添ったりする姿勢。
これは、関係性を育むうえでとても重要な要素です。
✅ トラブル時の対応が、叱るだけになっていないか
「ダメでしょ!」で終わるのではなく、
「どうして〇〇したの?」「〇〇くんはどう思ったかな?」といった声かけがあるかを見ることで、その園の保育方針の一端が見えてきます。
親の学びにもなる“保育者のまなざし”

保育者の関わり方に注目することで、親自身も「子どもへの接し方」を見直すヒントが得られることがあります。
- ✅子どもの気持ちをまず受け止める
- ✅感情に寄り添う言葉をかける
- ✅小さな成功や頑張りを一緒に喜ぶ
こうした姿勢は、園と家庭が連携し、子どもの育ちを支えるうえでとても大切。
ECERSは単なる園選びの基準ではなく、保護者としての“子どもとの関わり方”にも気づきを与えてくれるツールなのです。
まとめ|“見る保育”から“関わる保育”へ
- ✅ ECERSでは、保育者の関わり方を「子どもの心に寄り添っているか」という視点で評価します。
- ✅ 親としては、園見学の際に「保育者と子どもの距離感」「声かけの内容」「トラブル対応の仕方」などを見ることがポイント。
- ✅ そしてその視点は、親自身の子育てにも活かせる学びになります。
ECERSを通じて保育の“質”に触れることは、子どもを取り巻く環境をより良くする第一歩。
「うちの子が毎日安心して通える保育園って、どんなところだろう?」
その答えを、一緒に探していきましょう。